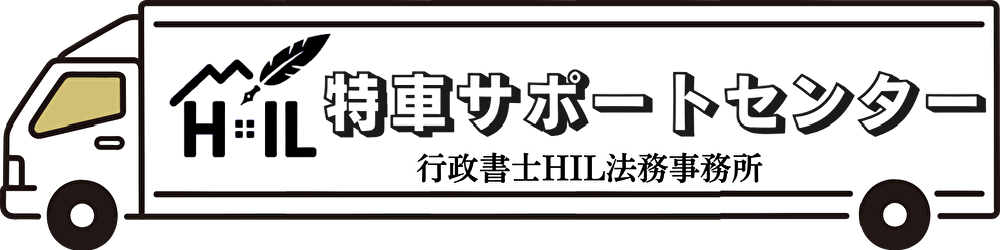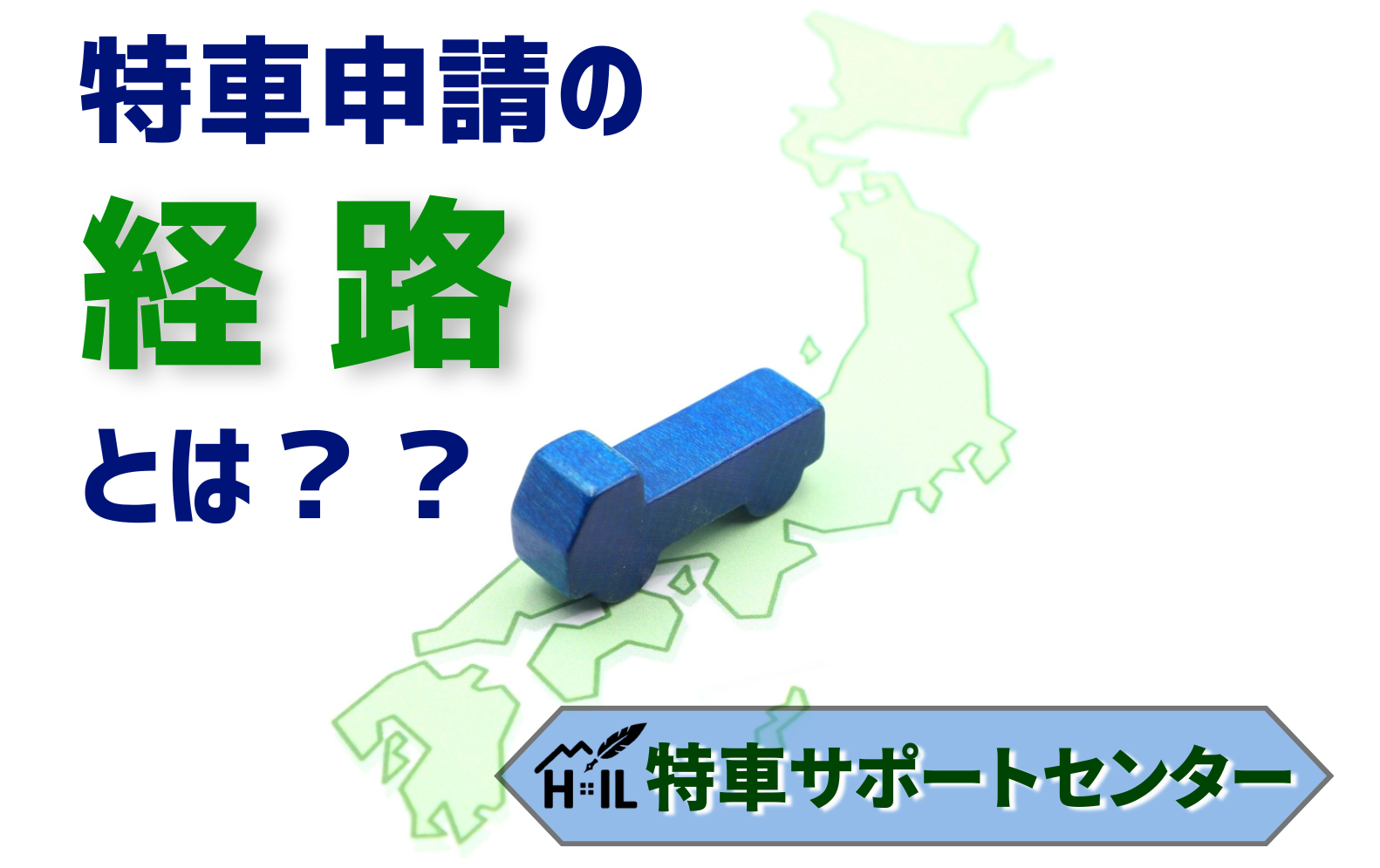特殊車両通行許可申請でも、特殊車両通行確認制度でも通行する経路について事前に申請若しくは確認をしなければならない。といった内容はご存じかと思います。
この特殊車両通行制度におけるこの「申請経路」や「確認経路」とは何なのか。いつも通行している道路と何が違うのかについて、ザックリとご説明します。
他のページに書いてあることをいい感じにまとめた内容となりますので、興味がないよという方は、左上の メニュー から気になるページへお進みいただくか、このまま無料見積もりをご依頼お願いします!
一般的制限値を知ろう
特殊車両通行許可制度も確認制度も予め通行予定の経路を決めなければなりません。
その気持ちは大変よくわかりますが、残念ながら車両の重さや長さによっては通行が制限される道路が数多くあります。
まず、どういった車両に通行できない道路があるのかと言いますと、下記に記された一般的制限値を1つでも越える場合、そういった車両は大前提として通行できない道路が多いです。
当然例外は存在しますが基本的にはダメです。
この一般的制限値を1つでも超える場合に必要になってくるのが、特殊車両通行許可又は通行確認です。
本来であれば通行が禁止されている道路を通行させるための許可及び確認となります。
許可証や回答書(確認OKですって証明です)を持って通行可能になります。
では、どのように申請をするのかと言いますと、専用システムに車両情報を事前に登録したり、通行したい経路が発生する毎に申請をしたり、車両の諸元や通行を希望する経路の情報を入力する必要があります。
今回は経路について詳しくご説明しますので、詳しくは各制度の概要をご確認ください。
特殊車両通行許可の場合
上記の一般的制限値を超える車両については、特殊車両通行許可や確認が必要ですが、当然、道路管理者としては過度に重い車両や長すぎる車両の通行を許可することには慎重になります。
道路の損傷や他の通行者の妨げになる懸念があるためです。
こう言った観点から、道路の損傷や他の通行者への影響を最小限に抑えるために、特殊車両通行許可が取得できた場合でも、経路に応じた条件が附されることがあります。
つまり、車両の種類によっては、同じ経路でも重量や長さが一定の基準を超えると、厳しい条件が付けられたり、通行が認められない場合があるということですね。
そのため、各申請車両ごとに経路を一つ一つ確認・選択し、厳しい通行条件が附されないか、通行禁止ではないかを確かめる必要があります。
さらに、国土交通省のシステムにデータがない未収録道路が含まれる場合、その道路を管轄する管理者を特定し、通行の可否を確認する手続きも必要となります。
これが特殊車両通行許可における経路の作成の流れです。
先ほど「一つ一つ」経路を選択すると言いましたが、基本的には交差点毎と思っていただいて差し支えありません。
直轄国道などの大型道路を直進する場合などは、交差点毎に区切らずに一直線で選択可能な場合が多いですが、やはり一般道路になるとそれでもかなりの数の経路を選択し確認する必要が出てきます。
実際の申請経験からお話しすると、ご依頼を頂いた事業者様が希望される経路を100%そのまま条件なしで通行できるケースは極めて稀です。
どうしても特定の経路を通行されたい場合は、誘導車をご用意い頂いたうえ、C条件やD条件を含んだ経路で許可を申請する形になります。
とはいえ、経路の作成段階で通行禁止や厳しい条件が附される点はある程度判別可能なため、条件の少ない経路を選択することで代替経路の作成は可能です。
貴社の事業プランに合わせて最適な経路を選んでいただければと思います。
特殊車両通行確認制度の場合
新制度と呼ばれる特殊車両通行確認制度の場合は、通行条件の心配や未収録道路の調査など、特殊車両通行許可制度で課題となる点の大部分が解消されています。
要するに、特殊車両通行確認制度では、専用システム上に車両を事前登録しておくことで、登録車両の走行が決まった後に出発地と目的地の情報を入力するだけで、自動的に経路が選択されます。
特殊車両通行確認制度について詳しく知りたい方はこちらのページをご覧ください。
一見便利に見える制度の半面、自動での経路作成となるため、希望する経路を細かく指定できず、未収録経路も選択されません。そのため、通行できない道路が多数あります。
特殊車両通行許可申請の経路作成は
貴社の希望に合わせて柔軟に選択可能ですが、経路の細部を確認しながら作成する必要があるため、容易とは言えない制度です。
一方、特殊車両通行確認制度は
経路選択が自動で行われるため、手間がかからず便利ですが、システム上に登録された主要な道路にのみ対応しています。
そのため、希望通りの経路を選ぶのは難しいです。また、車両の諸元によってはこの制度自体が利用できない場合もあり、制約の多い制度になります。
以上、特殊車両通行制度の申請経路、確認経路についてでしたが如何でしたでしょうか。
経路の作成において一長一短のある両制度ですが、双方を上手に採用して貴社の事業運営に活かして下さい。
特殊サポートセンターでは、特殊車両通行許可はもちろん、通行確認制度のご依頼も承っております。ご不明な点などございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。


最安値を追求
弊所に依頼するメリットの一つ目は、徹底したコストカットにより実現した圧倒的な低価格です。国道事務所から徒歩圏内に事務所を構えることで、行政庁との密な連携が必要な事案でも不要な交通費が発生しないため、低価格を実現できます。また、稼働率の低い図面作成等の業務を外部委託することで、申請の根幹を成す書類作成および経路図作成を低価格で提供できます。
特車申請に強い
弊所の行政書士は、国際物流の分野で約10年のキャリアを持ち、陸運および海運に関する知識と経験において他の行政書士を圧倒的に凌ぎ、特殊車両許可申請においては、許可率100%を維持しております。*2024年9月時点
成功報酬制度
弊所では、許認可全般について、法定手数料(行政庁への支払い)および費用が高額となる案件を除き、許認可の取得後にお支払いをいただいております。また、着手金をお預かりする場合でも、万が一不許可となった場合にはご返金しております。
充実したアフターサポート
一般的には有料のオプションサービスとなっている行政書士事務所が多い中、弊所では新規および更新に携わったすべての許認可申請について、次回更新期限の管理を無料で実施しております。定期的に現状確認としてご連絡いたしますので、許認可の内容に変更等があった際もお気軽にご相談ください。
各種お問合せはこちらから

-お問合せ-