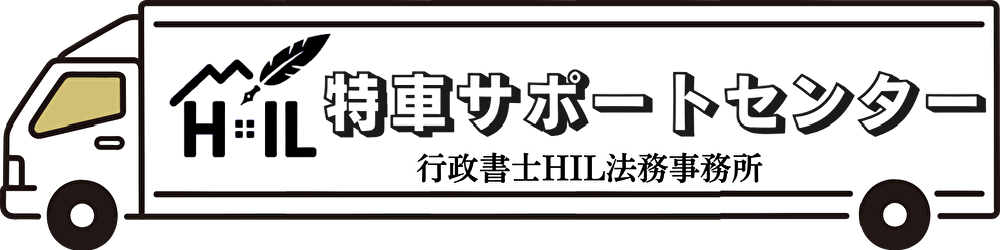特殊車両通行確認制度は、既存の特殊車両通行許可制度と並行し、迅速かつ簡便な手続きを提供するために令和4年から導入されました。
ここでは、従来の許可制度と新しい確認制度の違いや特徴について詳しく解説します。
特殊車両通行許可制度のおさらい
特殊な車両(車両の構造や輸送する貨物が特殊であり、幅、長さ、高さ、総重量などが一般的制限値を超える車両)は、道路を通行するために特殊車両通行許可が必要です。
特殊車両通行許可申請では、出発地と目的地に合わせて経路を作成するため、事業者様のご要望に応じ柔軟に経路の選択が可能です。
また、通行条件が良くない道路を事前に確認したり、国土交通省のシステムに収録されていない道路(未収録道路)についても調査のうえ対応が可能です。
特殊車両通行許可の有効期間は申請によって異なりますが、概ね2年または1年間となり、条件次第では最大4年間有効な許可の取得も可能です。
許可までの時間は車両や経路によって異ますが、申請後1カ月程度と考えていただければ問題ありません。
特殊車両通行確認制度の概要
特殊車両通行確認制度では、従来の許可制度に比べて申請作業や許可待ち時間が不要となり、確認後と即時に通行を開始することも可能です。
事前に車両を登録済みであれば、通行可能な経路の確認や手数料の支払いは24時間オンラインで行うことができます。
特殊車両の事前登録や廃止などの手続きも24時間オンラインで行えます。
因みに、特殊車両通行許可制度との根本的な違いは、基本的に申請者側で経路の作成をしない点です。
上記の「通行可能な経路の確認」とは車両情報等をシステムに入力し、自動で提示される経路の確認を言います。
特殊車両通行確認制度では、事前に登録した車両情報と経路確認時に入力した出発地、目的地の情報に基づき、国土交通省のシステムに登録された経路から走行可能な経路が自動で提示されます。
現時点では、通行可能な経路が大幅に限定されており、重要物流道路や大型車誘導区間などの一部の道路しか通行できません。
また個別協議が必要な道路や未収録経路も通行できません。
このことから、残念ながら出発地、目的地によっては本制度は利用することができませんが、事前登録の段階では車両を登録することができてしまうため、後述の 車両登録料は発生したが、肝心の経路確認はできない。といったケースも発生し得ます。
しかしながら、事前に通行確認が可能な経路が限定されている分、条件が整えばその日に通行することも可能となるため、非常に頼りになる制度だという点は押さえておきたいです。
細かい部分を解説
特殊車両通行確認制度は下記の様に2つの大きなフェーズに分割ができます。
➀車両の登録
事前に貴社の保有車両をシステム上に登録します。この登録は5年間有効で、更新が可能です。
ただし、全ての車両が登録できるわけではなく、ETC2.0車載器の搭載が条件となり、諸元(サイズ)も限定されています。詳細は以下の表をご参照ください。
登録手数料は1台5,000円で、トレーラーは登録不要です。
| 車種 | 右記以外 | セミトレーラ | フルトレーラ・ダブルス |
| 幅 | 一律3.5m 以下 | 同様 | 同様 |
| 重量 | 135.1t 以下 | 143.6t 以下 | 163.6t 以下 |
| 高さ | 一律4.3m 以下 | 同様 | 同様 |
| 長さ | 16m 以下 | 20m 以下 | 21m 以下 |
| 最小回転半径 | 車両の最外側の 轍について12m 以下 | 同様 | 同様 |
➁経路の検索
事前に登録済の車両の運行が決まりましたら、出発地と目的地の2地点を結ぶ「双方向検索」と指定都道府県内の全通行可能経路を検索する「都道府県検索」から一方の検索方法を選択し、経路の確認を行います。
- 2 地点双方向 2 経路検索(双方向検索)
出発地から目的地まで、主経路と代替経路の2経路が通行可能です。双方の経路間の渡り線も梯子状に通行できるため、混雑時の迂回なども可能です。 - 都道府県検索
選択した都道府県内の主要道路すべてを一括で確認して通行が可能となります。双方向検索よりも多くの路線が通行可能になりますが、法定手数料が割高になります。当事務所にご依頼を頂く場合は都道府県検索をお勧めしております。
経路の確認が完了し、法定手数料を納付した後に回答書が発行されます。
従来の特殊車両通行許可制度では許可証の携行が義務でしたが、確認制度では回答書の携行が義務となります。
名称は変わりましたが、書類の携行は引き続き必要です。(電子データも可)
特車許可と確認制度を比較
| 特殊車両通行許可制度 | 特殊車両通行確認制度 | |
|---|---|---|
| 手続き | ・車両登録は不要(申請時には車両情報の提示が必要) ・許可証の有効期間内は通行可能 | ・車両の事前登録が必要 ・5 年ごとに車両登録を更新 ・ETC2.0 の搭載が必要 ・1年間記録の保存が義務 |
| 期間 | ・申請から通行までは1カ月程度が目安(許可が下りるまで) ・許可の有効期限は最大4年 | ・経路確認後、即日通行が可能 ・回答書の有効期限は1年 |
| 経路 | ・通行したい経路を手作業で選択申請 ・経路選択の自由度が高い | ・システムで通行可能経路を自動表示 ・システムに収録された主要道路のみ |
| 対象道路 | 道路法上の道路全てが手続きの対象となりますが、 道路情報がデータ化されていない道路は個別協議が発生 | 通行できる道路の区間を経路図で表示 システムに収録された主要道路のみ |
| 手数料 | ・片道一経路200円 ・振込等による支払い | ・登録車両一台 5,000円 ・双方向検索 一件 600円 ・都道府県検索 200円~400円/県 ・キャッシュレス決済 |
| 携行書類 | 許可証及び関係書類一式 ( 電子データも可 ) | 回答書を携行 ( 電子データも可 ) |
| 必要情報 | ・申請の都度、車両諸元等の情報を入力 ・経路を作成して申請 | ・事前に車両情報を登録 ・経路を確認 |
上記の比較表からも明らかなように、特殊車両通行確認制度は従来の許可制度と比較して大幅に作業効率が向上し、申請後の長い待ち時間がなく、即時に回答書を受け取り通行が可能です。
しかし、私個人の感想としては、この制度はまだ発展途上であり、改善の余地があると感じます。
特殊車両通行確認制度は、従来の許可制度の不便さを補うために立案されたと認識しておりますが、従来の許可制度で必ずと言って良いほど発生し頭を悩ませる未収録道路の選択についてカバーするどころか、選択自体を不可能にしていると受け取れる内容で、細かい経路選択を望む事業者様には不向きな制度ではないでしょうか。
当然のことながら、特殊車両通行確認制度で認められた主要道路以外の脇道を少しでも通行すると法令違反になり、罰則の対象です。
また、この制度の有効期間は従来の許可制度よりも短く、経路によっては手数料も割高で複雑です。
現時点では、ほとんどの場合、特殊車両通行許可制度の方が業界のニーズにより適していると言えるでしょう。

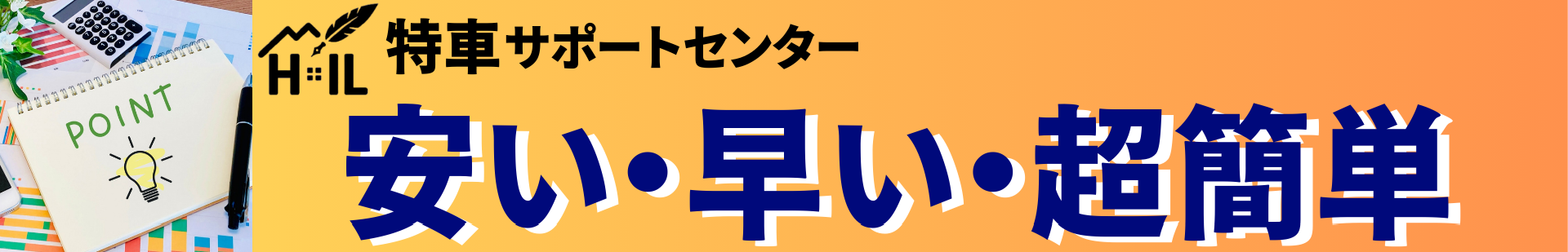
待っているだけでOK
お電話等のオンラインでお話しを伺い、必要書類をメールや郵送で送っていただきます。長々とお時間を頂くことも、当事務所へお越しいただく必要もございません。書類の作成から申請そして許可証の受領まで全て当事務所で請け負います。お客様はいつも通り事業にご集中いただきながら、当事務所からの許可の連絡をお待ち下さい。
成功報酬制度
当事務所では、許認可全般について、法定手数料(行政庁への支払い)および費用が高額となる案件を除き、許認可の取得後にお支払いをいただいております。また、着手金をお預かりする場合でも、万が一不許可となった場合にはご返金しております。
最安値を追求
徹底したコストカットにより実現した圧倒的な低価格でご案内致します。国道事務所から徒歩圏内に事務所を構えることで、行政庁との密な連携が必要な事案でも不要な交通費が発生しないため、低価格を実現できます。また、稼働率の低い図面作成等の業務を外部委託することで、申請の根幹を成す書類作成および経路図作成を低価格で提供できます。
とにかく早い
当事務所の実績として、特別な事情がある場合を除き、80%以上のお客様から、お問合せを頂いた翌日には必要書類をお預かりしております。ご通行を予定されている経路やその規模にもよりますが、必要書類をお預かりした後、即日又は翌日に申請を行ったケースも多くあり、お問合せから許可証のお渡しまで10日間の事例もございます。
各種お問合せはこちらから

-お問合せ-