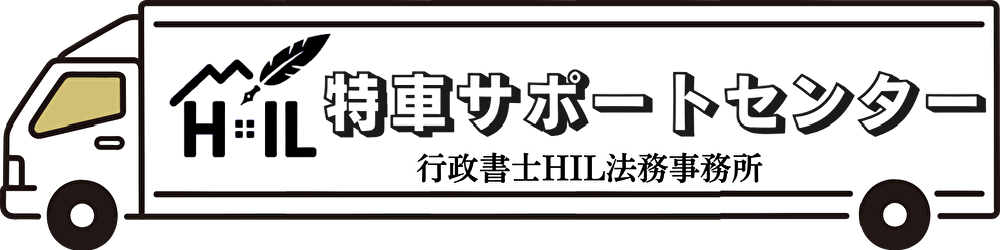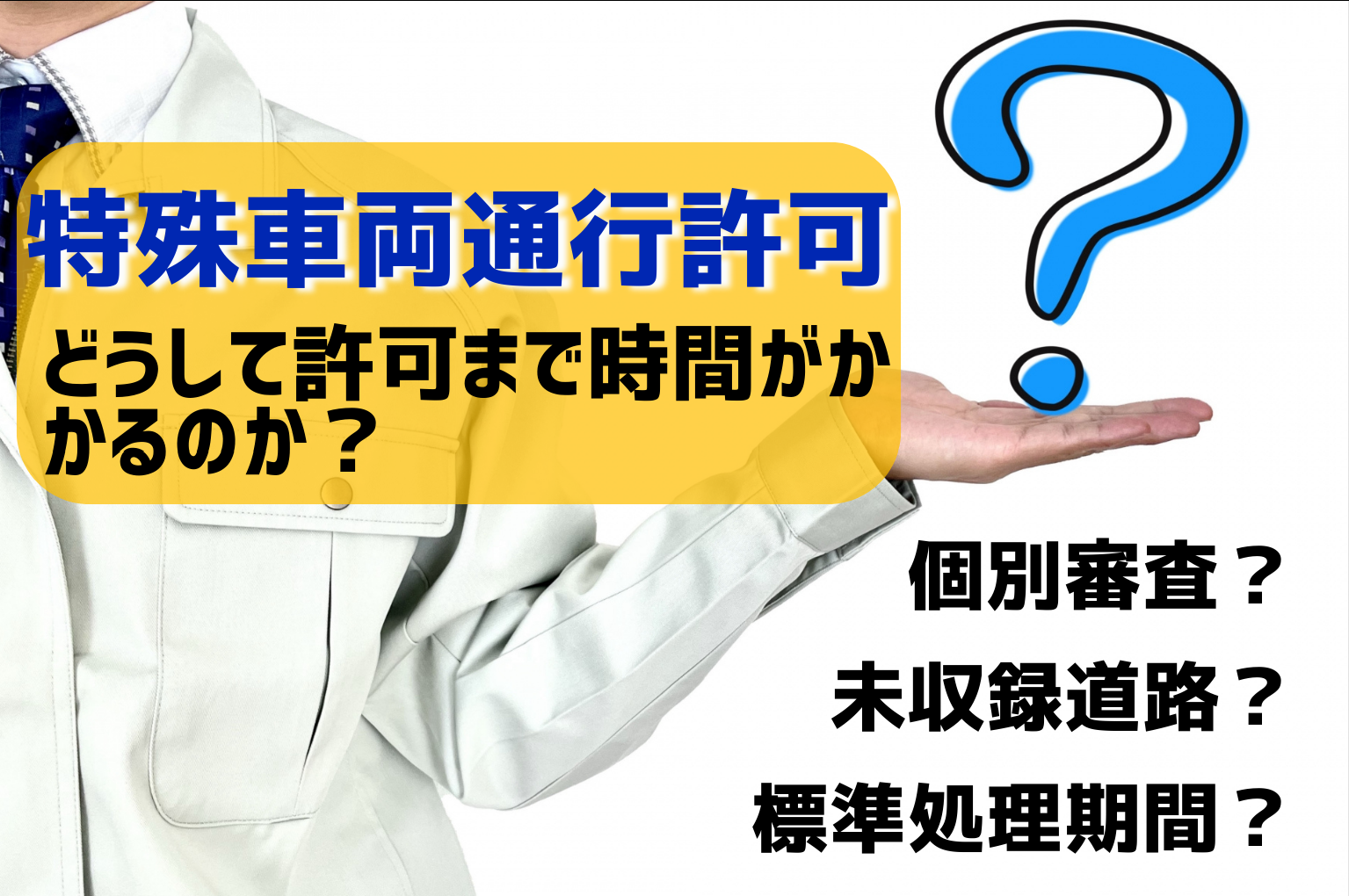特殊車両通行許可申請を何度か経験された事業者様であれば「どうしてこんなに時間がかかるんだろう」と思ったことはありませんか?
行政から受ける許可(許認可)には許可または不許可の処分を下すまでにかかる標準的な期間が定められております。
今回は、特殊車両通行許可申請の標準的な処理(許可または不許可)までの期間や、長くなりがちな理由についてお話していきます。
標準処理期間
特殊車両通行許可に限らず、申請をしてから、許可や不許可の処分を受けるまでの期間のことを「標準処理期間」といいます。
特殊車両通行許可申請の場合は、申請を受けた道路管理者が、特殊車両通行許可の基準に照らして、その特殊車両が申請された経路を通行可能かどうか審査をします。
特殊車両通行許可の標準処理期間は新規申請及び変更申請で3週間程度、更新申請で2週間程度とされています。
標準処理期間はあくまで目安の期間として捉えていただく必要があり、標準程度の基準を満たす申請の場合は上記の標準処理期間内で処理されるであろうと考えられます。
国土交通省の通知事項を参考に標準程度の基準として以下の3つが挙げられます。
- 申請経路が道路情報便覧記載路線(国土交通省のシステム上に収録済の路線)で完結していること
- 申請車両が超寸法車両及び超重量車両(特殊車両通行許可限度算定要領による許可限度寸法、重量を超える車両をいう。)でないこと
- 申請後に申請内容(申請経路や諸元等)の変更が無いこと
標準処理期間は、これらの基準をすべて満たす場合を想定しています。
このため、全ての基準を満たしたうえで、申請に何らの不備が無い場合は最短で1週間以内に許可が下りることもあります。
反対に、上記の基準を満たさず、申請にも不備がある等の場合には許可までに2カ月以上かかってしまうこともあり得ます。
先述の標準程度の基準について少し深堀していきましょう。
標準程度の基準について
特車申請の標準処理期間は、申請自体が標準程度の基準を満たしている場合を想定しているとお話しました。
国土交通省の通知事項によると、これには上記の通り3つの基準がありますが
➂申請後に申請内容(申請経路や諸元等)の変更が無いこと
こちらについては、申請後に変更があれば審査の期間が延びるのは普通の事ですので、詳細については割愛します。
経路の基準
➀申請経路が道路情報便覧記載路線(国土交通省のシステム上に収録済の路線)で完結していること
要するに未収録道路はありませんか?ということです。
未収録道路についてはこちらのページでも解説していますので、ご確認ください。
申請した経路全てが国土交通省のシステム上に収録されているの道路の場合は、許可の基準に照らしてシステマチックに処理が行われます。
しかし、収録されていない道路(未収録道路)が含まれる場合には、他の道路管理者との協議などの個別の審査が必要となりますので、その分審査期間が長引く事になります。
とはいえ、全国の道路の約7割以上は未収録道路と言われておりますので、この基準を満たすのは簡単なことではありません。
国土交通省は日々収録道路を更新するように努めておりますし、協議を受けた道路管理者についても、速やかに審査を行い回答することを求められている為、審査の速度は年々向上してはいます。
近い将来全て全国全ての道路が収録道路となることを我々行政書士は節に切に願っております。
車両の基準
➁申請車両が超寸法車両及び超重量車両(特殊車両通行許可限度算定要領による許可限度寸法、重量を超える車両をいう。)でないこと
特殊車両通行許可が必要となる場合、多くのケースでは一般的制限値の寸法(車幅、車高、車長)や、総重量を超過する事になると思いますが、この一般的制限値を基準に考えると、この基準に示されている「超寸法車両及び超重量車両」はもう一段階上の別の基準を超える車両を指します。
というのも、いくら一般的制限値を超過した車両に与える許可が特殊車両通行許可だと言っても、際限なく大き車両や重い車両を同じ基準で許可していくことは現実的ではありません。
そこで行政は、超寸法や超重量といった上位の定義を設け、「超寸法車両及び超重量車両」に該当する場合は、事前相談や軌跡図等の追加書類をを求める一段厳しい対応を取っています。
超寸法車両や超重量車両で特車許可を申請すると、先ほどの事前相談や、追加資料だけでなく、まず間違いなく個別審査が必要になります。
個別審査とは、申請した経路を申請車両が物理的に通れるかなどを協議を受けた各道路管理者が個別に検討を行って許可または不許可を判断するために行う審査です。
狭小幅員、橋梁、交差点、未収録道路などで個別審査が発生しやすい為、超寸法車両や超重量車両では99%個別協議が行われるでしょう。
標準処理期間は個別審査が必要となる場合を想定していませんので、超寸法車両や超重量車両の申請では、最低1カ月以上はかかるものと考えて挑んで下さい。
申請先の道路管理者にもよりますが、すでに多くの個別審査案件を抱えている道路管理者が関与する場合は、審査に要する期間が数カ月に及ぶことも覚悟しなければなりません。
早急に特殊車両通行許可が必要な場合は、可能であれば「超寸法車両及び超重量車両」の申請は避けるようにしましょう。
まとめ
標準処理期間についての内容でしたが、申請から許可までに時間がかかる理由、お分かり頂けましたでしょうか。
全経路で未収録道路を避けて、車両も超寸法や超重量とならないように…ってなかなか大変ですよね。
超寸法車両及び超重量車両での申請を避ける事や、未収録道路を通らない様にすることは大切ですが、申請者側で可能な根本的な対策としては、まず申請書を最短で仕上げる事、そして審査の早い窓口に申請をすることです。
先ほどご説明した通り、すでに多くの個別審査案件を抱えている道路管理者が係る場合、審査に要する期間は必然的に長くなります。
このため、道路管理者毎に処理の速度に違いは出てきます。(ちなみに、国道事務所としては「どこの国道事務所も審査速度は同じ」という見解だそうです)
我々行政書士は、書類作成のプロとして、申請書を最短で仕上げる事は当然のこと、当事務所の様に特殊車両通行許可に精通した行政書士は審査の早い窓口も多く熟知しております。
特殊車両通行許可の取得を検討中の事業者様はぜひ特殊車両通行許可に精通した特車サポートセンターまでお問い合わせください。

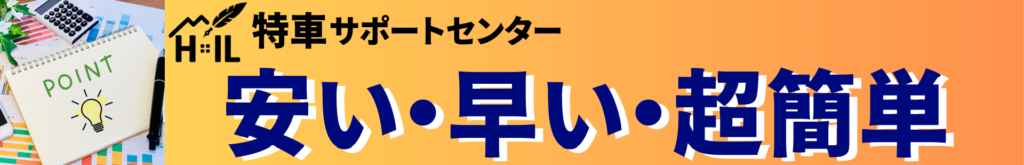
待っているだけでOK
お電話等のオンラインでお話しを伺い、必要書類をメールや郵送で送っていただきます。長々とお時間を頂くことも、当事務所へお越しいただく必要もございません。書類の作成から申請そして許可証の受領まで全て当事務所で請け負います。お客様はいつも通り事業にご集中いただきながら、当事務所からの許可の連絡をお待ち下さい。
成功報酬制度
当事務所では、許認可全般について、法定手数料(行政庁への支払い)および費用が高額となる案件を除き、許認可の取得後にお支払いをいただいております。また、着手金をお預かりする場合でも、万が一不許可となった場合にはご返金しております。
最安値を追求
徹底したコストカットにより実現した圧倒的な低価格でご案内致します。国道事務所から徒歩圏内に事務所を構えることで、行政庁との密な連携が必要な事案でも不要な交通費が発生しないため、低価格を実現できます。また、稼働率の低い図面作成等の業務を外部委託することで、申請の根幹を成す書類作成および経路図作成を低価格で提供できます。
とにかく早い
当事務所の実績として、特別な事情がある場合を除き、80%以上のお客様から、お問合せを頂いた翌日には必要書類をお預かりしております。ご通行を予定されている経路やその規模にもよりますが、必要書類をお預かりした後、即日又は翌日に申請を行ったケースも多くあり、お問合せから許可証のお渡しまで10日間の事例もございます。
各種お問合せはこちらから

-お問合せ-