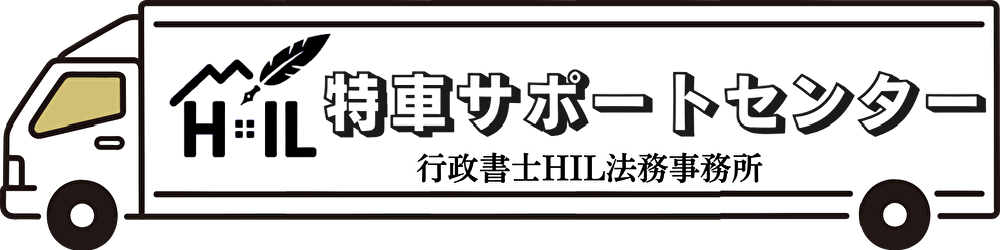今回は特殊車両通行許可の包括申請についてお話します。
比較的マイナーな許可である、特殊車両通行許可の中で更にマイナー(個人の見解です)な包括申請ですが
具体的には同じ車種(海上コンテナ、スタンション型セミトレーラ等の括り)であり、なおかつ同じ車軸である場合に限って、同一経路間での同一内容の許可を包括的に得られる申請になります。
一般的には1台毎に経路や積載貨物を記載した申請書を提出して審査のうえ許可を受ける必要がありますが
例えば、同一車種で同一車軸の車両10台などを、総重量や経路、有効期間などを統一して包括的に許可を受けられるます。
メリットどデメリットを比較
包括申請を行うメリットとしては、当然申請回数は大幅に削減されることが期待され、手間が省けますし、1件1件その都度許可を申請しなくて良いので、必然的に許可証の枚数も少なくなり管理が非常に簡単になります。
特殊車両通行許可制度の難点の一つに、「許可証の管理」が挙げられます。
もちろんPDF形式等で端末上に許可証を保存することも認められておりますが、紙媒体で管理されている事業者様が多いような印象を受けます。
許可の件数が多いと管理する許可証の量もそれに伴い増加しますので、複数の車両の許可を1つの申請で取得できる包括申請はこの点においてメリットが大きいと言えます。
反対にデメリットとしては、包括申請の場合は諸元や経路を考慮のうえ一番条件の厳しい車両をベースにした合成車両数値(数値上の架空の車両数値)を元に審査が行われますので、
個別の申請と比べると審査状況が厳しくなると言わずるを得なく、車両1台当たりに積載可能な重量は多くの場合で減少となります。
| 自重 | 軸重A | 軸重B | |
|---|---|---|---|
| 車両➀ | 6.8トン | 4.2トン | 2.6トン |
| 車両➁ | 6.6トン | 4.4トン | 2.2トン |
上の例だと、それぞれの赤字の重量が申請車両の中で最も大きい数値となる為、この数値を機械的に組み合わせた合成車両で許可の判断が行われます。
そうすると、車両➁については、実際の自重よりも重い重量として扱われますし、後軸の軸重も実際より重いものとして審査されます。
したがって、必然的に総重量は実際の車両より重いものとして計算される為、積載可能な貨物の重量は個別で申請を行う場合と比べて減少します。
このように、包括申請では審査時に想定される車両の諸元を実際に通行する車両の諸元が上回ってしまう事の無いように、 包括申請された複数の車両の諸元から最も条件の悪い数値を取り出して許可の判断を行うため
最終的な許可の条件は個別に申請する時よりも厳しいものになります。
また、包括申請をした複数台の内、1台でも変更が生じた場合は許可を維持することはできず、変更後の組み合わせで再度包括申請を行い、許可を受ける必要があります。
申請や管理が楽になるという1点のメリットに対して、発生するデメリットが若干大きいようにも感じますが、現に利用される事業者様もいらっしゃいますので、ぜひ興味があれば特車サポートセンターまでお問合せ下さい。

各種お問合せはこちらから

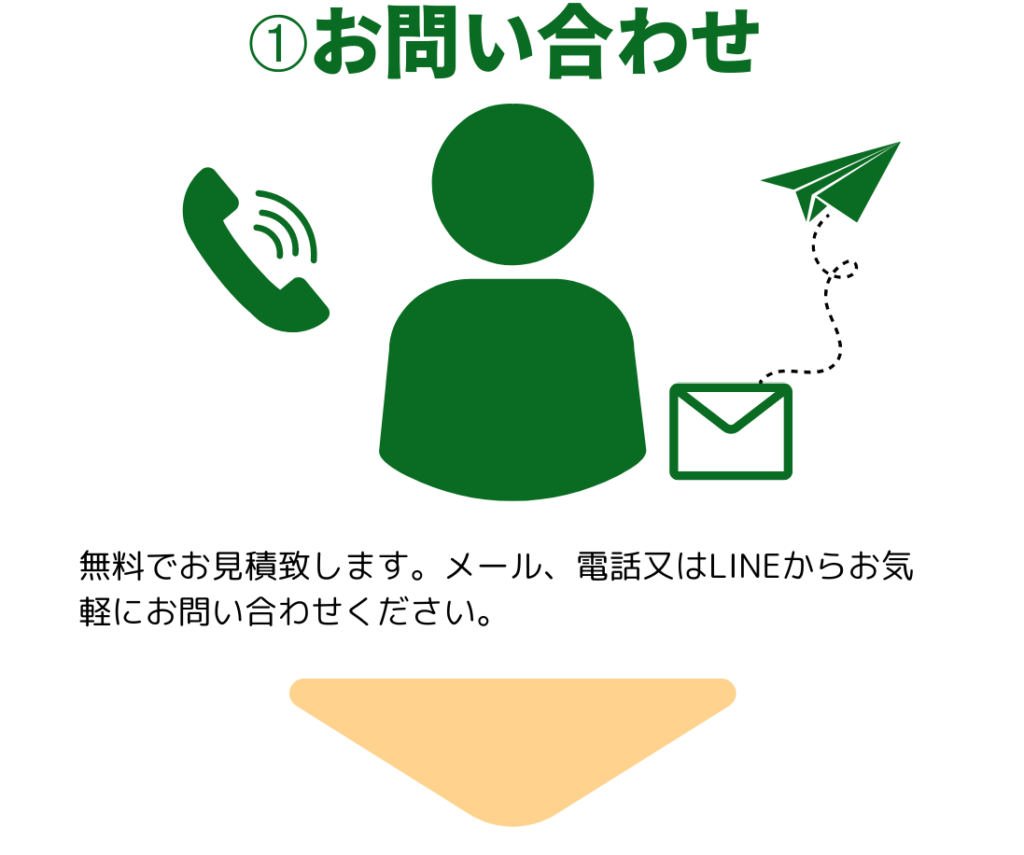
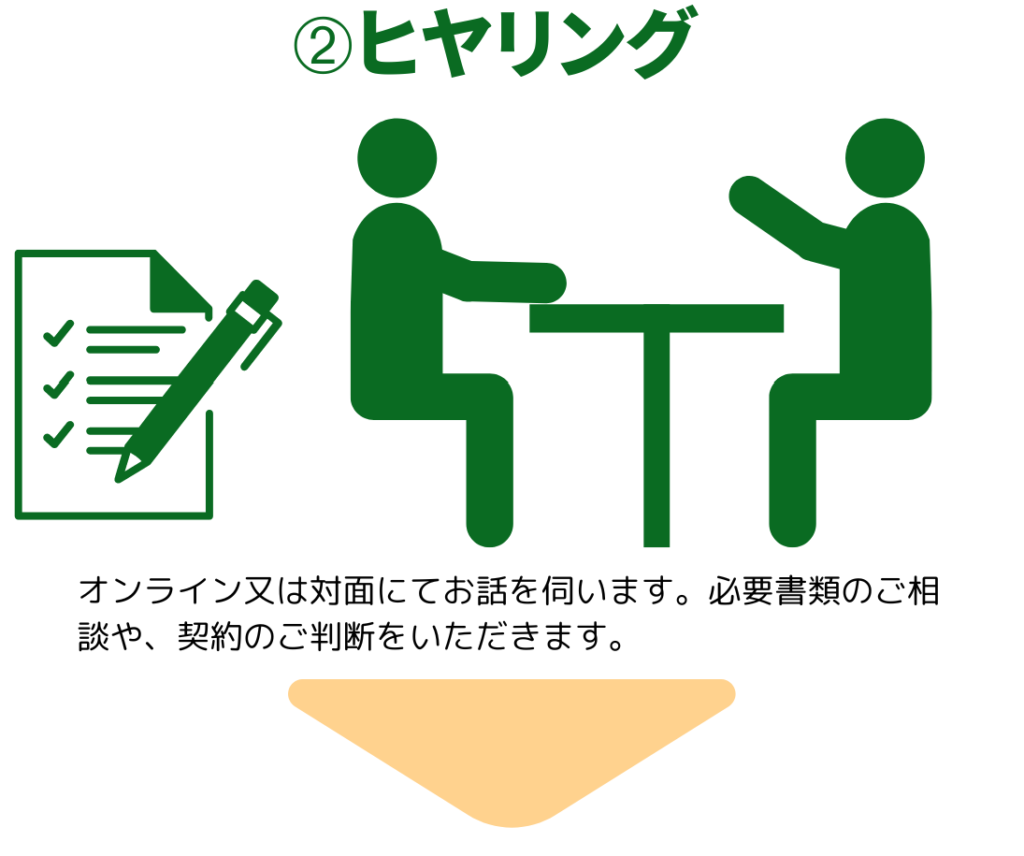
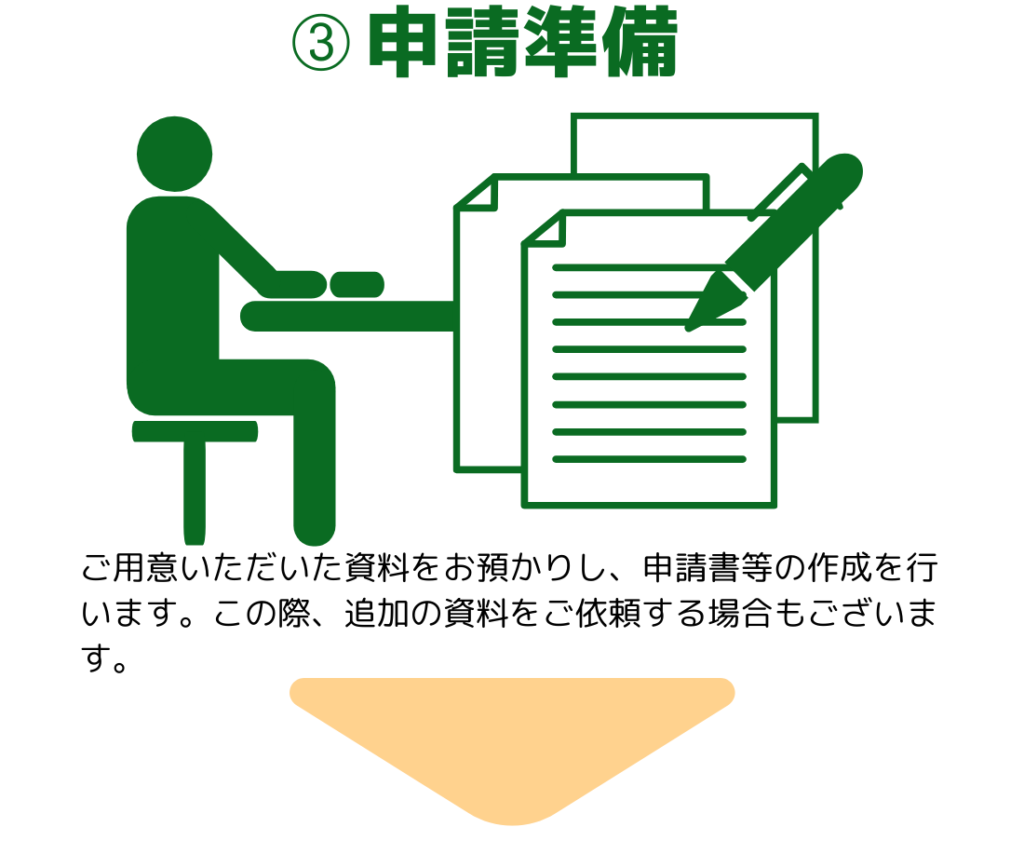
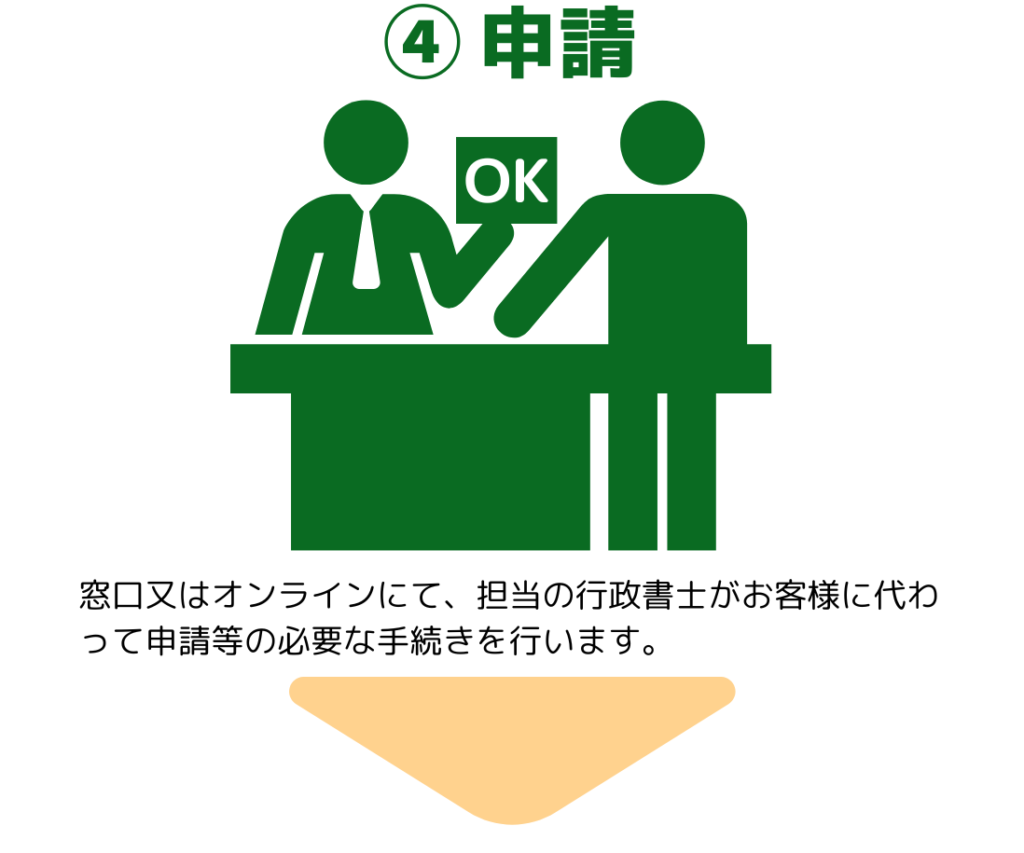
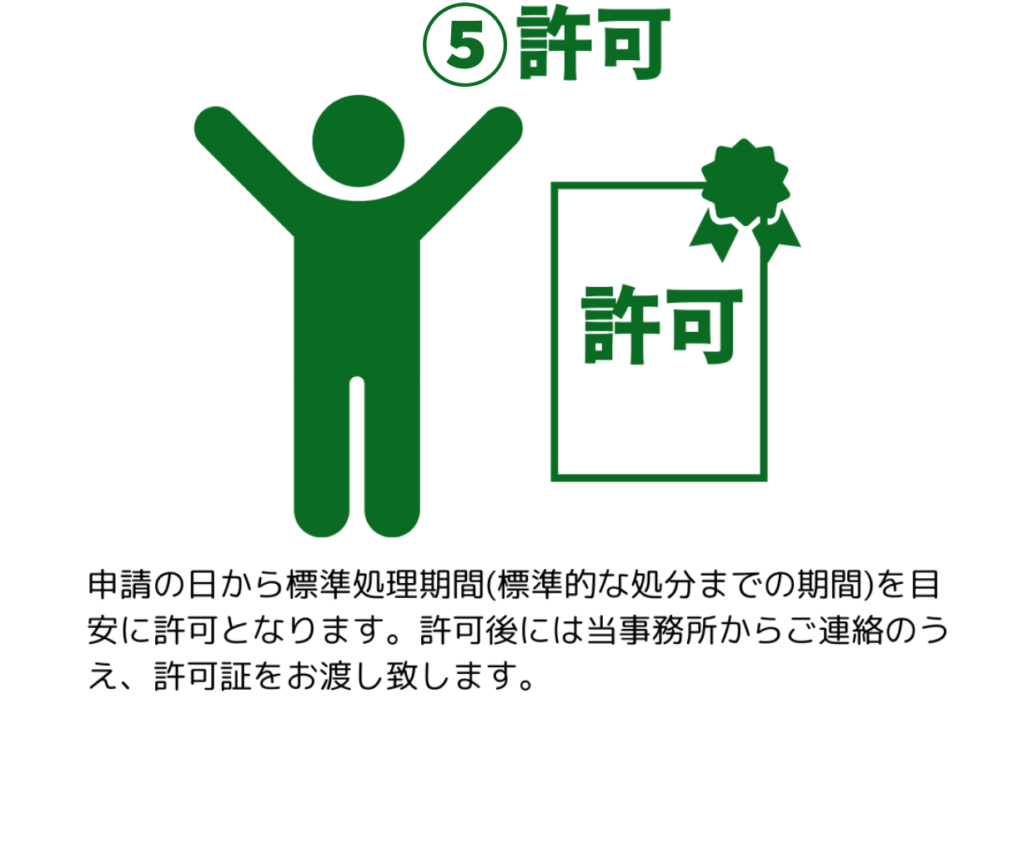

-お問合せ-