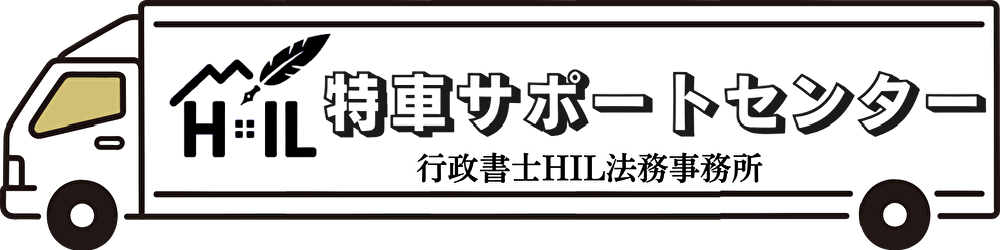特殊車両通行許可は取るのにも一苦労ですが、許可の取得後も正しく運用してこそ効果が発揮されます。
せっかく許可を取得したのに、条件違反で罰則の対象になってしまっては大変残念ですよね。
ここでは実際に事業者様が特殊車両通行許可を取得された後、何をすればいいのか?といった疑問にお答えします。
特殊車両通行許可とは
私たちがいつも利用する道路のほとんどは、特定の重量や寸法(以下「一般的制限値」と呼びます)を持つ車両が安全かつスムーズに通行できるように設計されています。
一般的制限値を超える車両は、道路の構造や交通に悪影響を与える可能性があるため、基本的には通行が禁止されています。
しかし、道路は社会や経済活動を支える重要なインフラであり、社会経済的な理由から一般的制限値を超える車両の通行が必要になることがあります。
このため、道路管理者が車両の構造や積載貨物が特殊であると認めた場合に限り、道路の構造を保護し、交通の安全を確保するための条件を設定して、これらの車両(「特殊車両」と呼びます)の通行を可能にする制度が設けられています。
それでは晴れて特殊車両通行許可が下りて許可証を取得した後に事業者様は何をすれば良いのでしょうか。
以下に注意点としてまとめました。
許可後の注意点
➀許可証の携行
取得した許可証を運行時は常に備え付けてください。
許可を取得しても許可証を備え付けていなければ無許可と同等の罰則の対象となります。 – 道路法第104条第2号
また、摘発時に許可の存在を証明する責任はドライバーを含む事業者側にあります。
備え付けているはずだけど場所が分からない、他の許可証と混ざってどの許可証が必要か分からない
このような事が無いように許可証一式は適正に管理してください。
現在では許可証の電子携行も可能なので、PDF等のファイル形式で端末内に保管していただくことをお勧めします。
➁通行経路
許可を取得した経路のみが通行可能となります。
許可証に付帯する通行経路表並びに通行経路図をよく確認してから走行してください。
冒頭で述べた通り、特殊車両の通行は基本的に禁止されております。
禁止されている事柄が、一定の条件の元(特車申請の場合は一定の経路に限り)許可されているものと捉えてください。
許可された2つの道路相互間を結ぶ未許可の道路でも通行はダメです。 許可されなかったのには必ず理由があります。道路の構造を保護し、交通の安全を確保を最優先に通行しましょう。
➂許可条件
上記の通行経路と内容は重なりますが
許可に付された条件は必ず守りましょう。
A B C D の通行条件や、誘導車の配置、夜間通行条件等これらの条件も必要があるから附されているものになります。
条件違反も当然罰則の対象となります。 – 道路法第103条第5号
とはいえ、夜間通行条件や誘導車を配置するのは容易なことではありません。
人件費もかかりますし、車両を新たに用意する必要も出てくるかもしれません。
せっかく取得した許可の条件に違反するよりも、積荷を少し減らして重量を軽くしたり、少し遠回りして大型車誘導区間を中心に走行するなど、対策はいくらでもあると思います。
申請の前段階でこう言った点もぜひご検討下さい。
通行条件についての詳細はこちらのページも合わせて読んでみてください。
④許可の期限
有効期限の切れた許可証は使えません。
許可証には有効期間が記載されております。
概ね1年から2年の事が多いでしょう。
この有効期間内に限り通行が許可されている為、期限後は無許可状態になります。
無許可の場合は当然これも罰則の対象ですね。
許可の有効期限をよく確認し、期限後も引き続き同様の経路を通行する必要がある場合は、期限の2カ月ほど前には更新申請をしましょう。
大きな注意点としては以上の4点となります。
せっかく取得した特殊車両通行許可ですから、間違っても不携帯や、条件違反で罰則を受ける事の無いよう適正に管理して、貴社の事業発展に活かしてください。
特車サポートセンターでは、新規許可のご依頼を頂いた全ての許可について許可期限の管理を行っております。有効期限の2カ月前にご連絡を差し上げますので、ぜひご利用下さい。


6ヵ月以下の懲役又は100万円以下の罰金
特殊車両通行許可が必要な場面で、許可を取得していない、条件に違反している、または許可証を携行していない場合、取締り等によりそのことが発覚すると、違反の程度に応じて100万円以下の罰金または6ヶ月以下の懲役が科される可能性があります。
高速道路割引の停止
高速道路入口付近などでは、高速道路各社による取締りも行われております。
特殊車両通行許可違反などの発覚により、高速道路割引の停止や、ETCカードの資格停止など、現在受けている恩恵が一気に失われる可能性があります。
この事実は、貴社の円滑な事業運営や今後の発展の大きな障壁となることは言うまでもありません。
荷主勧告制度
運送事業者等が無許可などの違反行為について取締りを受けた際に、その違反行為の責任が荷主にもあると判断された場合、荷主に対して再発防止のための勧告が行われると法律に定められております。
荷主からの厳しい到着時間の指定も荷主勧告の対象になり得る為、運送事業者、荷主双方に法令遵守に対する意識が必要です。
特車許可の取得事業者は増加中
近年、運送事業者自体の数は大きく変化しておりませんが特殊車両通行許可の取得件数は平成29年から令和3年の間で 約1.4倍 となっております。
これは今まで特殊車両通行許可を取得していなかった事業者様がどんどん許可を取り始めているということです。
各種お問合せはこちらから

-お問合せ-